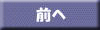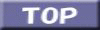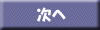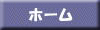日記とか...(^^ゞ
  |
| カメラが壊れたときの心理 | ||||||||
| ||||||||
| 完動品かジャンクか | ||||||||
| ||||||||
| 近年のカメラと昔のカメラ | ||||||||
| ||||||||
| PENTAX SP (ユキノフさんからの頂き物) | ||||||||
| ||||||||
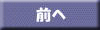
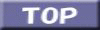
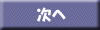
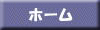
- Topics Board -
Skin by Web Studio Ciel

  |
| カメラが壊れたときの心理 | ||||||||
| ||||||||
| 完動品かジャンクか | ||||||||
| ||||||||
| 近年のカメラと昔のカメラ | ||||||||
| ||||||||
| PENTAX SP (ユキノフさんからの頂き物) | ||||||||
| ||||||||